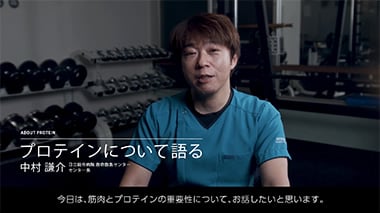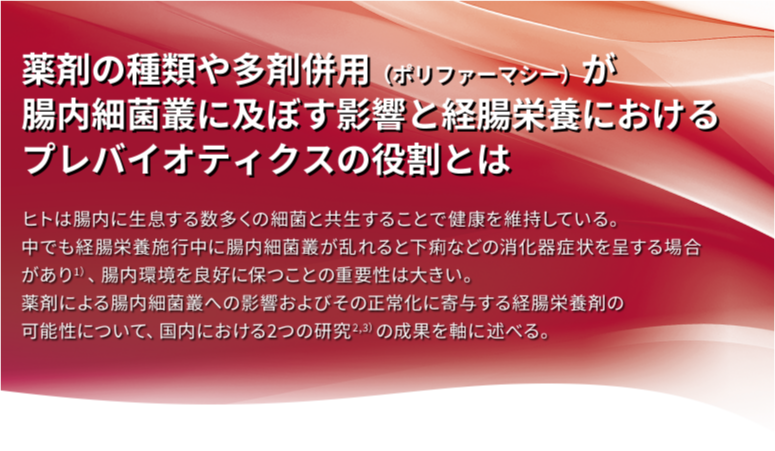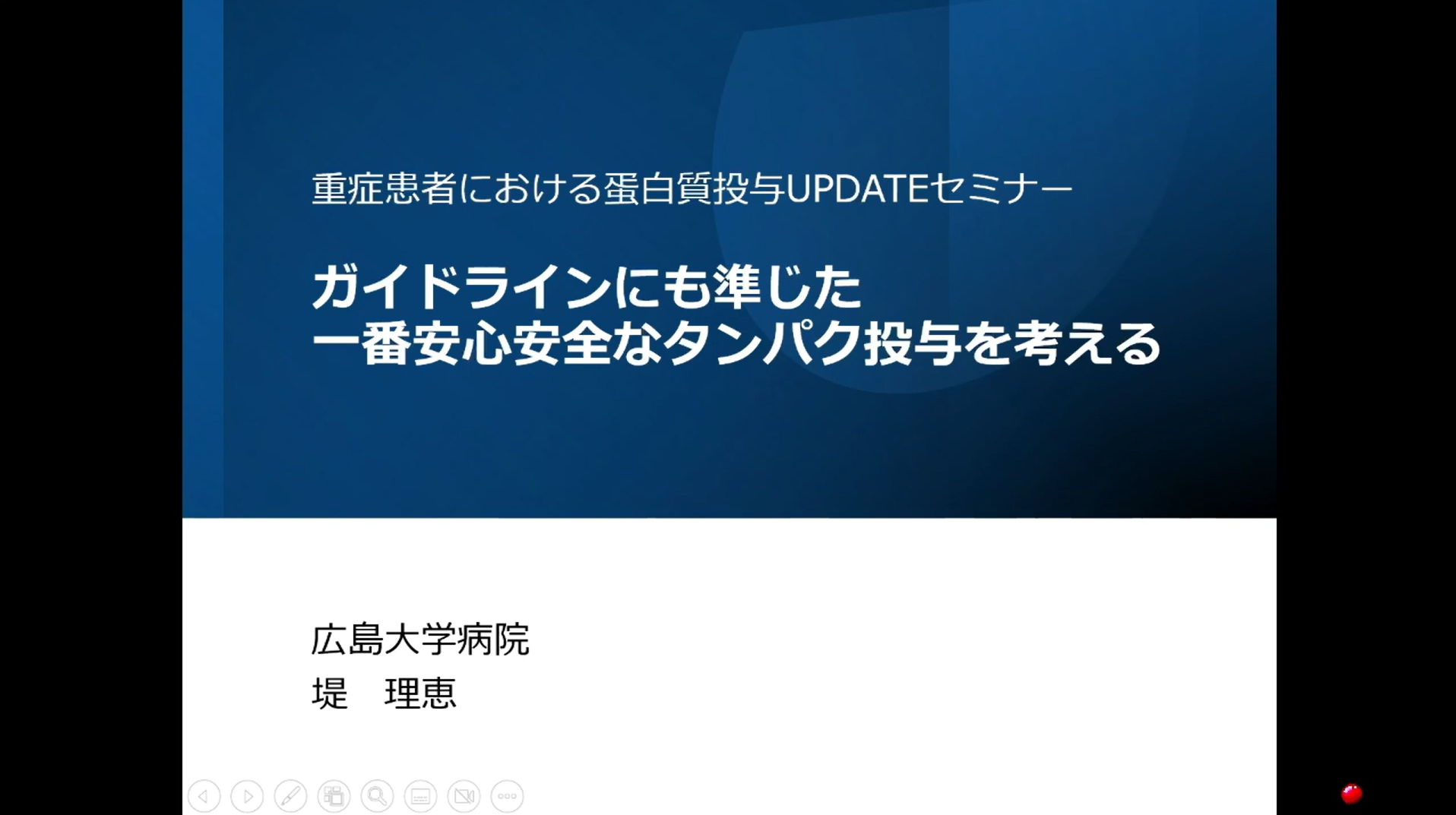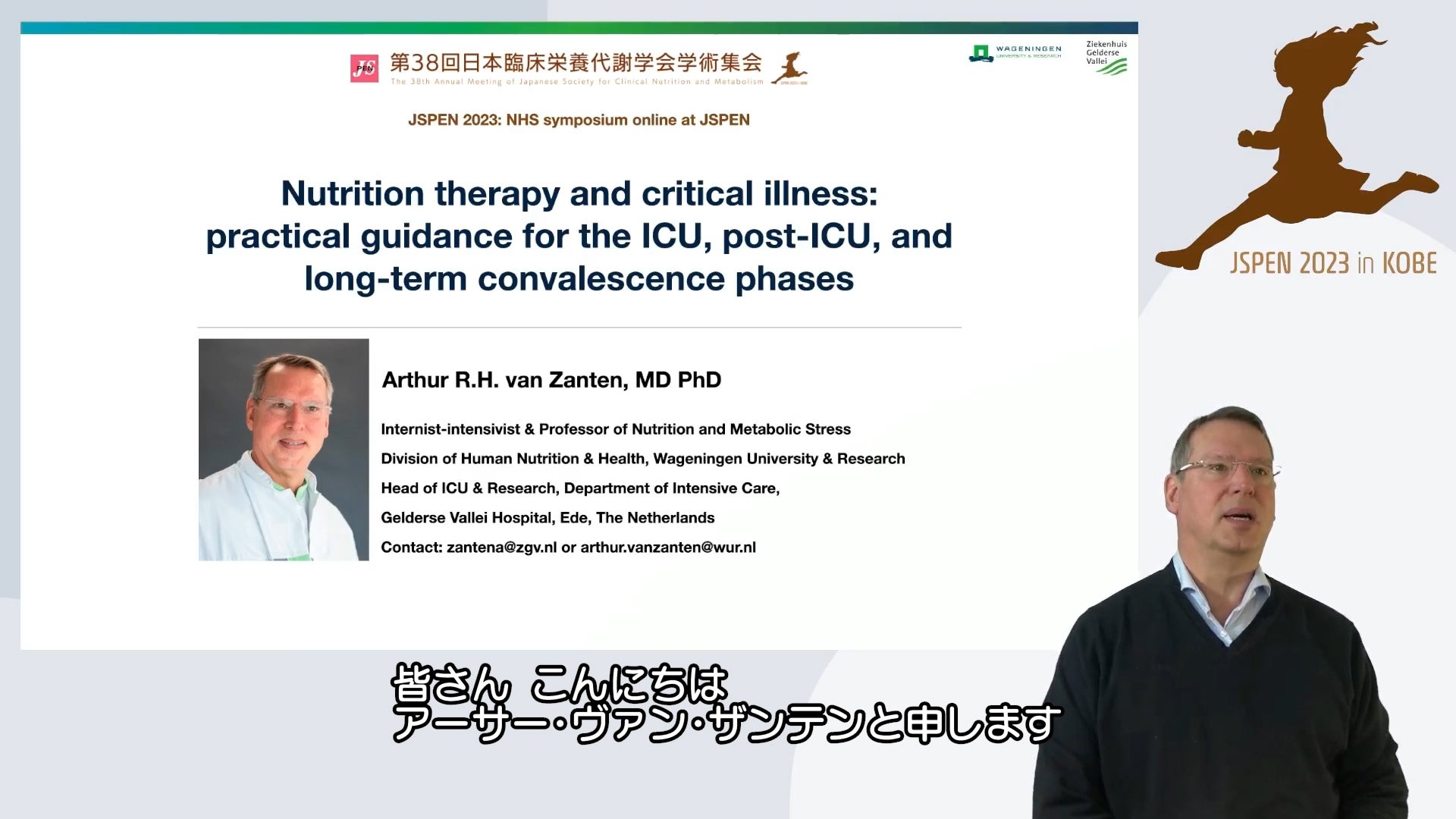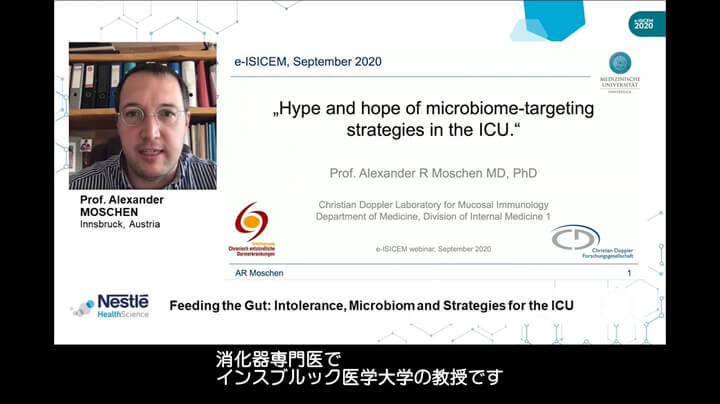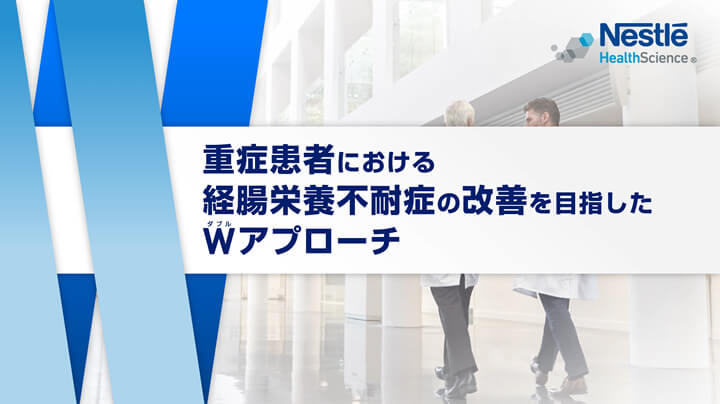回復期慢性期

回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事
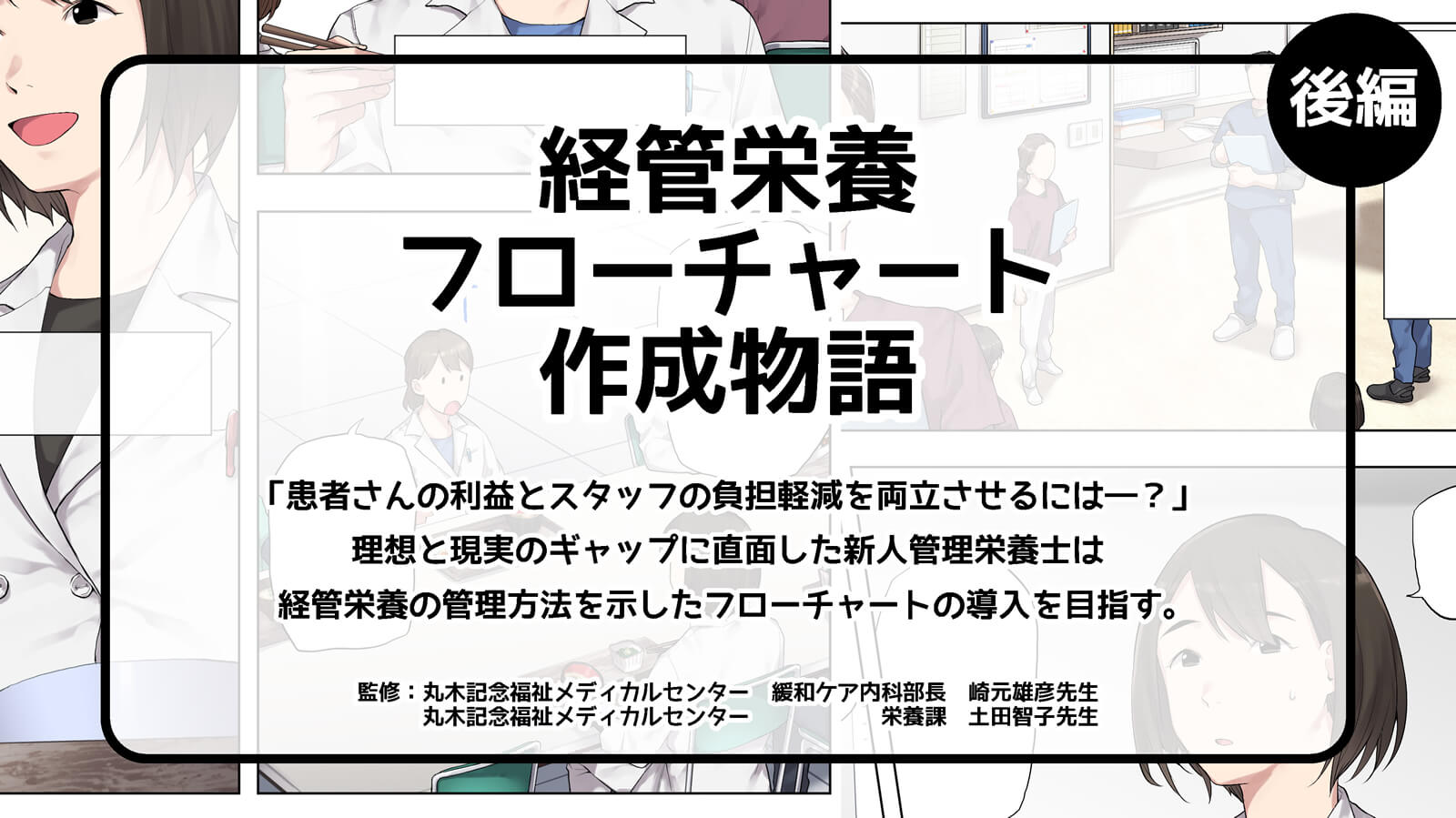
回復期慢性期
記事
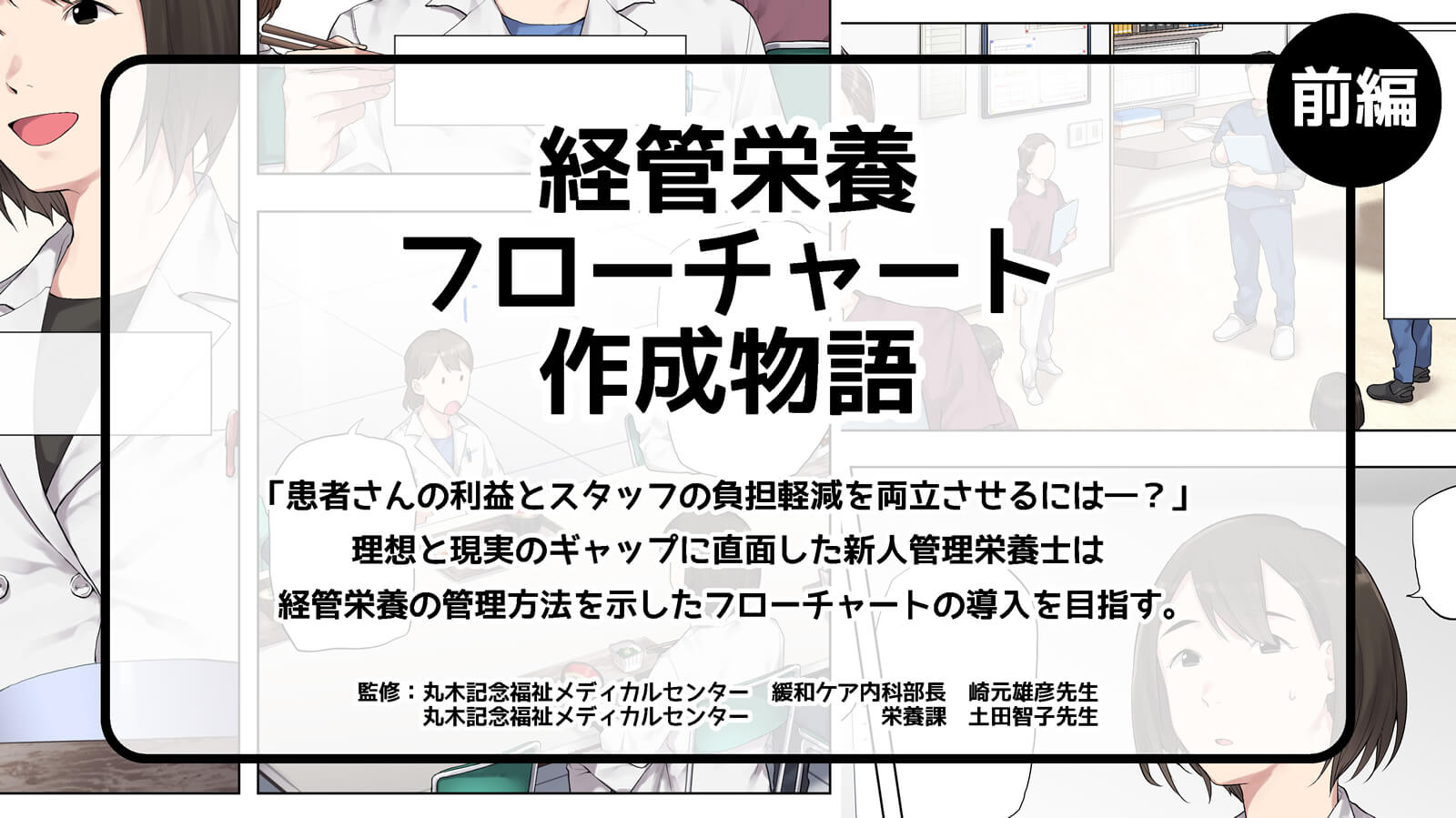
回復期慢性期
記事
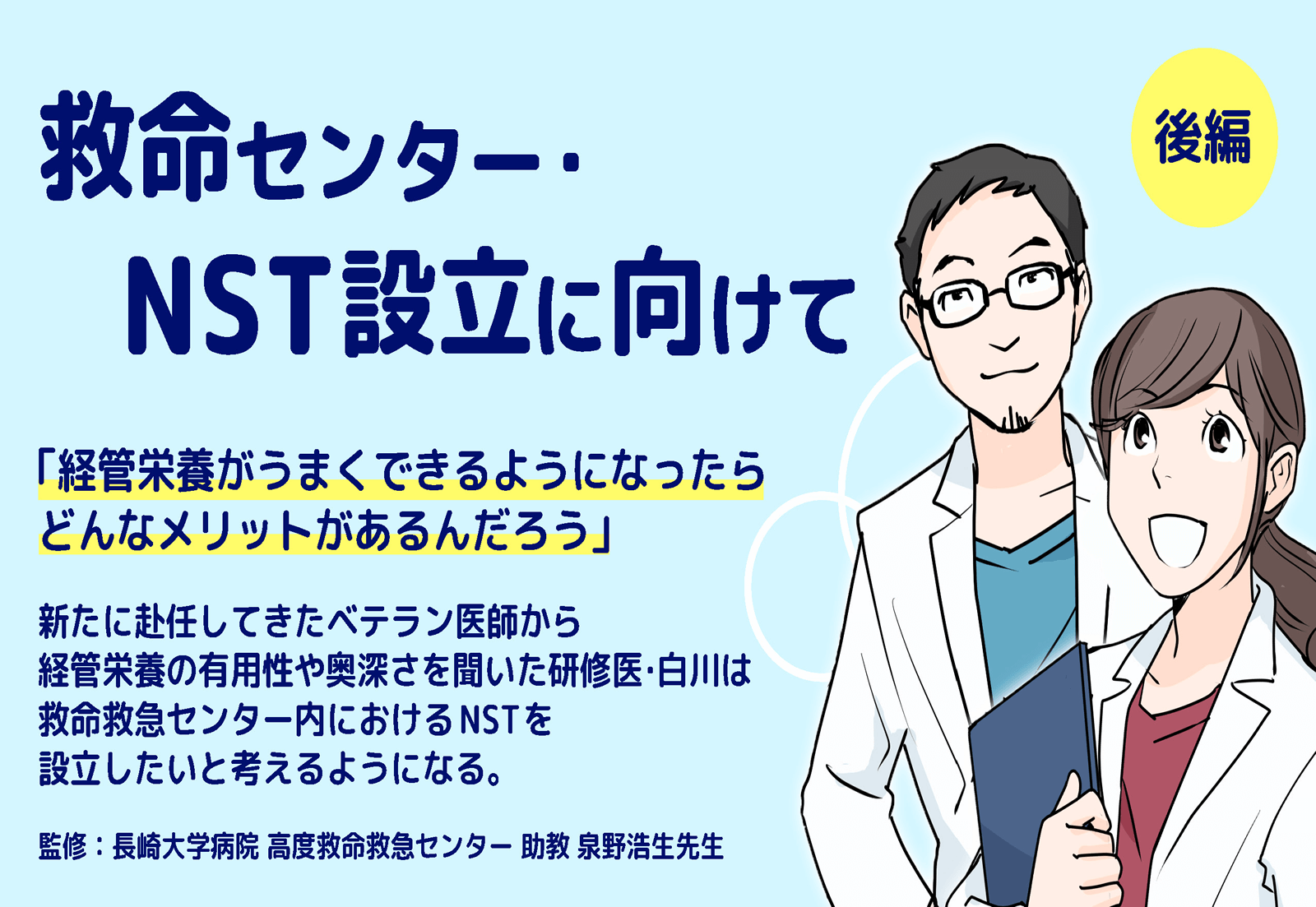
回復期慢性期
記事
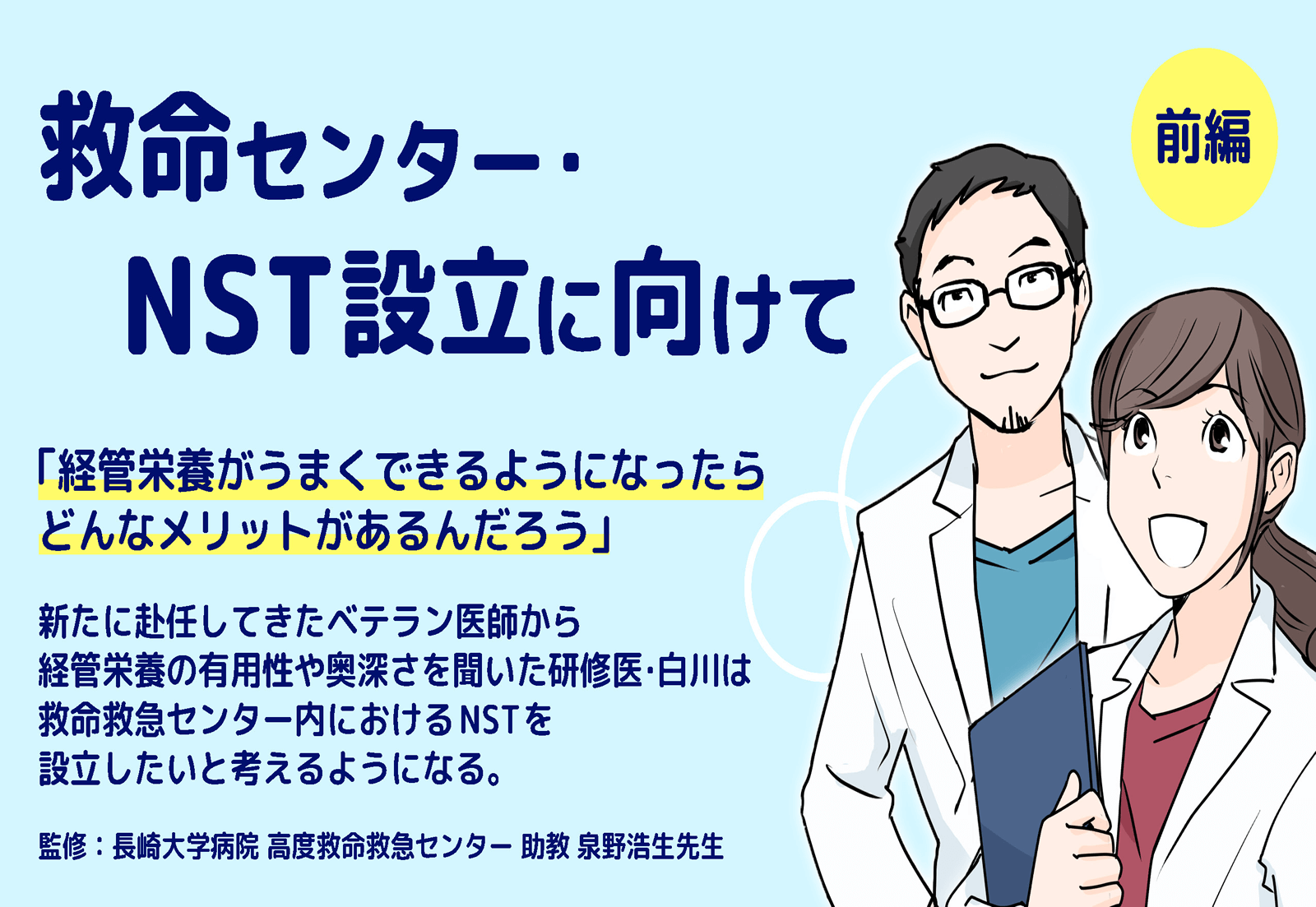
回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事
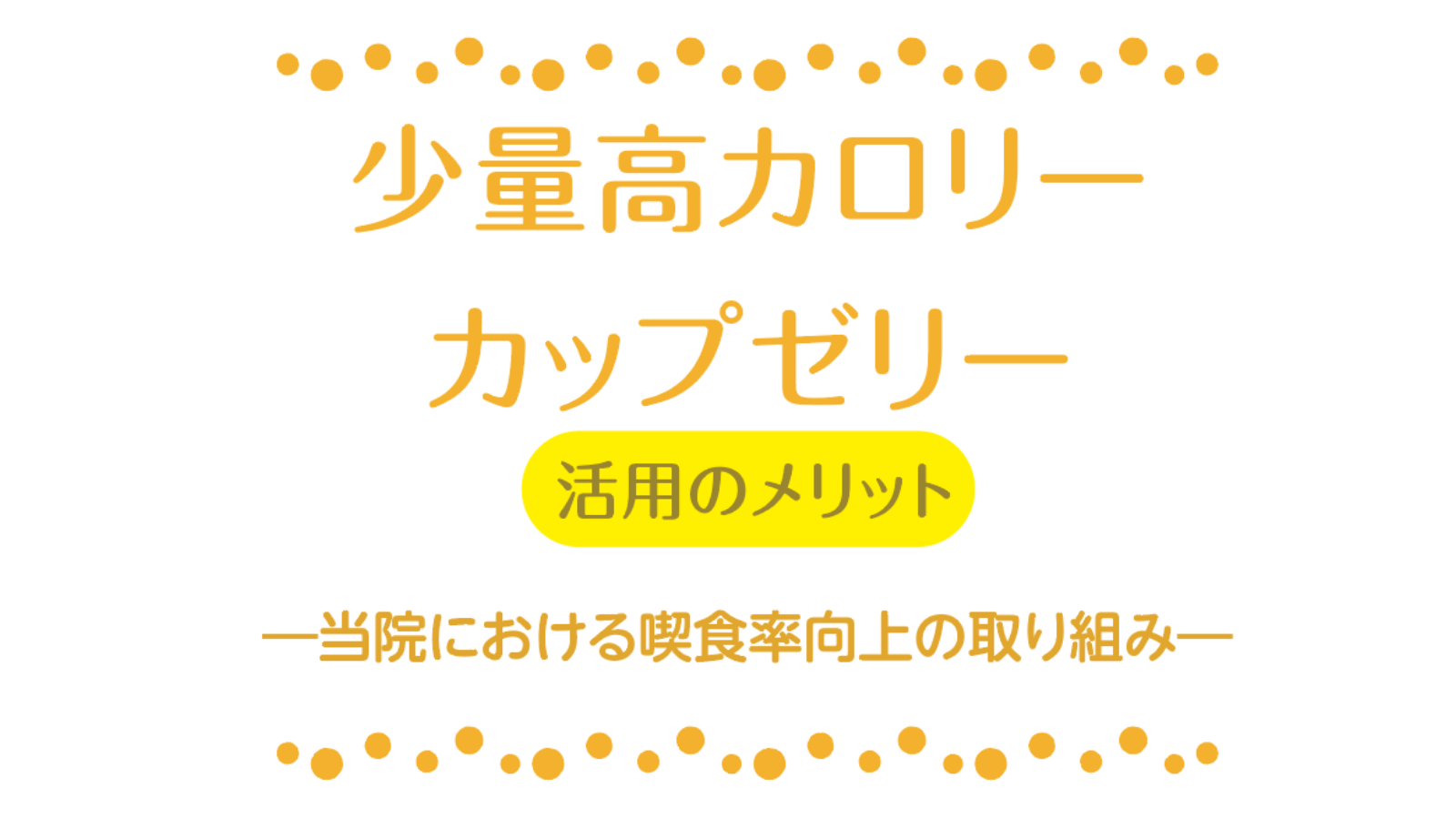
回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事

回復期慢性期
動画
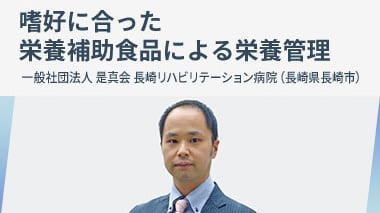
回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事
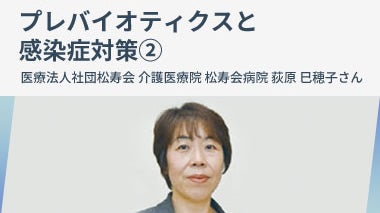
回復期慢性期
記事

回復期慢性期
記事
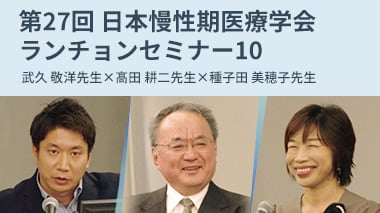
回復期慢性期
記事
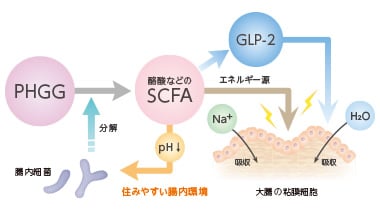
回復期慢性期
記事
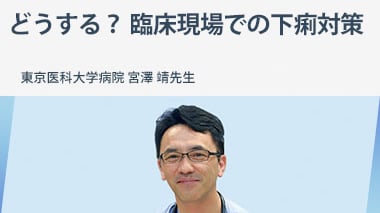
回復期慢性期
記事
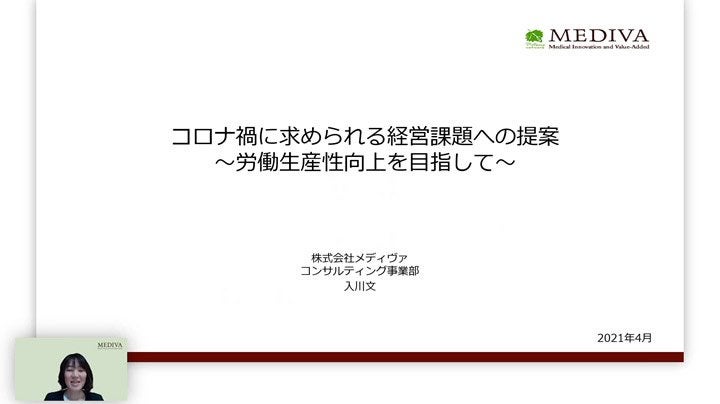
回復期慢性期
動画
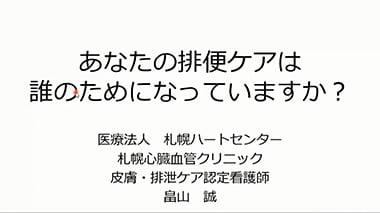
回復期慢性期
動画
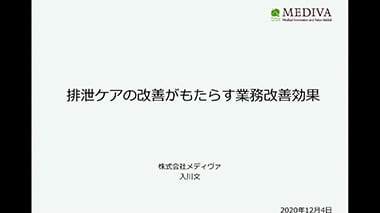
回復期慢性期
動画

回復期慢性期
動画
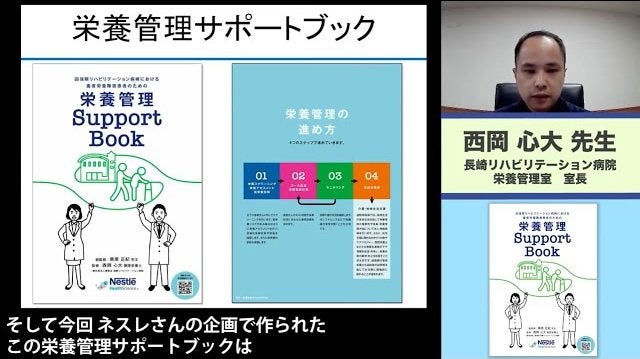
回復期慢性期
動画
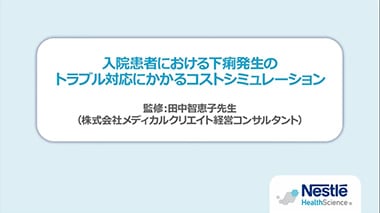
回復期慢性期
動画

回復期慢性期
動画
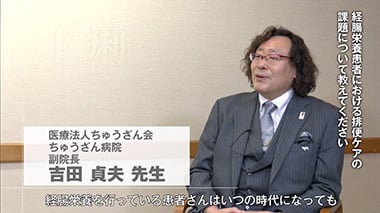
回復期慢性期
動画
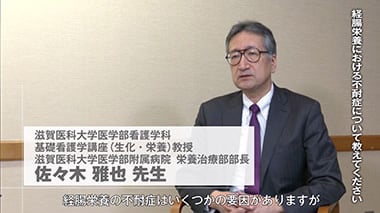
回復期慢性期
動画
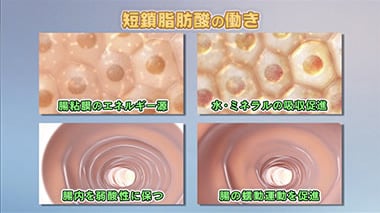
回復期慢性期
動画

回復期慢性期
動画

回復期慢性期
動画
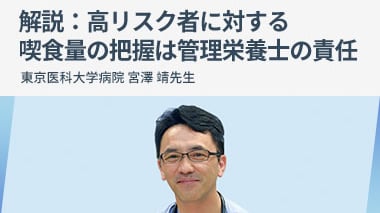
回復期慢性期

回復期慢性期

回復期慢性期

回復期慢性期

回復期慢性期
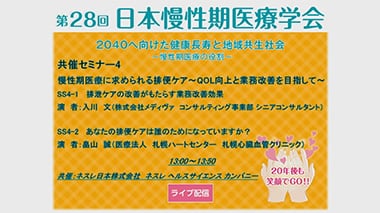
回復期慢性期
動画

回復期慢性期
動画
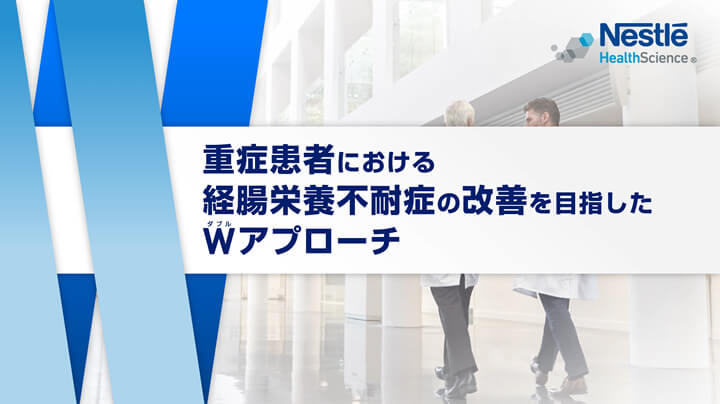
回復期慢性期
動画

回復期慢性期
動画